美術品買取|古美術やかた【京都・東京】
美術品取り扱い一覧
仏教美術
仏教美術は大きく大別して、仏像、仏具、絵画、があります。
美術品の中では歴史も古く、江戸時代や室町時代の作品では、古くても大きな評価をされる品物は少なく、 西暦1000年頃の平安時代の作品に高価な品が多くあります。
また、仏像やその他の作品にも時代の約束事のようなものがあり、 例えば、一般的に、仏像の中がくりぬかれているものは古く、 顔の面が前のほうで割れている作品は新しく、後ろのほうで割れている作品は古いというように聞いております。
仏像
如来
真如の世界より来られし者で、修業を完成して、悟りを開いた人の意味。
- 頭部が盛り上がっている。
- 頭髪が右巻に渦巻いている。
- 眉間から伸びた身長くらいの長さの白い毛が右巻に渦巻いている。
- 体が金色である。
- 装飾品は身に付けない。
- 衣服は衲衣と裳を纏っているだけ。
- 持物は持たない(例外有り)
三十二相八十種好「さんじゅうにそうはちじっしゅこう」とは、仏の身体の特徴を表す。
見てすぐに分かる三十二相と、微細な特徴、八十種好を合わせたこと。
菩薩
成仏を求め修行を積む人の意味。
- 上半身に条帛を纏い、下半身に裳を着け、天衣が両肩から垂れ下がっている。
- 髻を結い上げて宝冠を頂き、胸には瓔珞(胸飾り)、耳には耳トウ(イヤリング)、腕には腕釧、臂釧、 足には足釧などの装飾品がある。
- 如来のように印は結ばず、それぞれ持物を持っている。
- 多くが立像である。
明王
仏教に帰依しない民衆を力づくでも帰依させるための役割を担った仏尊。
- 不動明王
- 降三世明王
- 大威徳明王
- 金剛夜叉明王
- 大元帥明王
- 愛染明王
- 孔雀明王
- 馬頭明王
恐ろしい外貌と激しい憤怒の相が特徴。
天部
仏教に帰依した神々で、仏教を信ずる心を妨げる外敵から人々を守る仏像。
- 梵天
- 帝釈天
- 持国天
- 増長天
- 広目天
- 多聞天(毘沙門天)
- 弁才天(弁財天)
- 大黒天
- 吉祥天
- 韋駄天
- 歓喜天
仏具
- 本尊:信仰の対象として最も大切に安置される
- 仏壇:厨子
- 三具足:仏具の呼称の一つ、香炉・燭台・花立で一組
- 五具足:三具足に燭台と花立を一つずつ足した物
- 経典:法句経、阿含経、般若経、維摩経、涅槃経、華厳経、法華三部経、等々
その他、香炉、香合、経机、燭台、瓔珞、金剛杵、梵鐘、如意 等々
日本の仏教絵画
飛鳥時代や奈良時代の現存仏教絵画は、一般にはほとんど無いため、平安時代の作品からご紹介致します。
平安時代前期
平安時代初期には、空海、最澄らの僧が相次いで中国・唐へ留学し、日本へ系統的な密教を伝えました。
彼ら入唐僧は、両界曼荼羅などの密教図像を数多く日本へもたらしました。 両界曼荼羅は密教の世界観を象徴的に表わしたもので、空海将来の原本に近いものとされています。 両界曼荼羅はその後の時代にも引き続き多く制作され、その他、各種の曼荼羅や仏画が制作されました。
| 代表的な作品 |
両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【神護寺】 両界曼荼羅(伝・真言院曼荼羅)【東寺】 真言七祖像の龍猛、龍智像(他五点は唐画)【東寺】 十二天像【奈良 西大寺】 不動明王像(黄不動)【園城寺】 |
|---|
平安時代後期
平安時代後期には、源信の影響で、西方極楽浄土への再生を願う浄土信仰や末法思想が広まりました。 この時代には阿弥陀如来来迎図、浄土図などが多く描かれました。
| 代表的な作品 |
普賢菩薩像【東京国立博物館】 十二天像【東寺伝来・京都国立博物館蔵】 仏涅槃図【高野山金剛峯寺】 阿弥陀聖衆来迎図【高野山有志八幡講】 平等院鳳凰堂壁画【平等院】 平家納経の見返し絵【厳島神社】 |
|---|
鎌倉時代
鎌倉時代には、仏教絵画は多彩になり、祖師像を仏像と同様に尊重しました。大徳寺の大燈国師像などがこの時代の代表作です。
この時代の仏画は、平安時代のものに比べて墨線を強調しており、様式的には宋の影響が強く出ています。
近世
近世にも形の上では障壁画、屏風絵、ジャンルの上では文人画、琳派、円山四条派、浮世絵などさまざまな絵画が描かれました。
明治時代には岡倉天心の指導を受け、多くの古い仏画の模写が行われ、新しい仏画が描かれました。 狩野芳崖の悲母観音図はその代表作といえます。
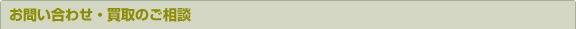
-
美術品買取に関するお問い合わせや美術品買取のご相談は、メール・お電話などでお気軽にどうぞ! 美術品買取のご相談は定休日も含めて毎日AM9:00〜PM9:00まで受付けております。
メールにて画像を添付してお問い合わせいただく場合は、 yakata-@mb.infoweb.ne.jp
までお願いいたします。(メールソフトが起動します)