美術品買取|古美術やかた【京都・東京】
ホーム > 美術品 買取 取り扱い作家
楽吉左衛門―らくきちざえもん
略歴
千家十職の一つ。
楽焼の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々襲名している名跡。
当代は十五代。
三代 道入以降の各当主には隠居した際、
「入」の字を含む入道号が贈られており、
後世にはその名前で呼ばれる事が多い。
| 初代 長次郎 〜天正17年 (〜1589) |
|
|---|---|
| 二代 常慶 永禄4年〜寛永12年 (1561〜1635) |
田中宗慶(長次郎の補佐役と目される)の次男。 大降りでゆがみのある茶碗、「香炉釉」と呼ばれる白釉の使用を始める。 本阿弥光悦と交流があった。 |
| 三代 道入 慶長4年〜明暦2年 (1599〜1656) |
別名「ノンコウ」。 多数の釉薬を使用する明るい作風が特徴。 |
| 四代 一入 寛永17年〜元禄9年 (1640〜1696) |
三代の息子。 初代を模範としつつ、父の技法を取り入れ、 地味な色調の中に光沢を持つ作風を特徴とする。 |
| 五代 宗入 寛文4年〜享保元年 (1664〜1716) |
四代の婿養子。 28歳の時「吉左衛門」襲名。 長次郎回帰を進める。 |
| 六代 左入 貞享2年〜元文4年 (1685〜1739) |
五代の婿養子。 「光悦写し」の茶碗に定評がある。 |
| 七代 長入 正徳4年〜明和7年 (1714〜1770) |
六代長男。 茶碗以外に香合や花入れなど多数の作品を制作。 |
| 八代 得入 延享2年〜安永3年 (1745〜1774) |
七代長男。 父の隠居に伴い1852年に襲名するが、病弱のため、父の死後に弟に家督を譲り隠居。 その後も制作を続けるが30歳で早世。 25回忌の時に「得入」と賜号され、正式に歴代の中にはいる。 |
| 九代 了入 宝暦6年〜天保5年 (1756〜1834) |
七代次男。 「三代以来の名工」とされ、へら削りの巧みな造形に特徴がある。 |
| 十代 旦入 寛政7年〜嘉永7年 (1795〜1854) |
九代次男。 文化8年(1811)襲名。 表千家九代了々斎と共に紀州徳川家に伺候、「偕楽園窯」開設に貢献。 その後「西の丸お庭焼き」「湊御殿清寧軒窯」などの開設にも貢献した功績により、 文政9年(1826)、徳川治宝より「樂」字を拝領。 作風は織部焼、伊賀焼、瀬戸焼などの作風や意匠を取り入れ、技巧的で華やかとされる。 |
| 十一代 慶入 文化14年〜明治35年 (1817〜1902) |
十代婿養子。 弘化2年(1845)襲名。 明治維新後、茶道低迷期の中、 旧大名家の華族に作品を納めるなど家業維持に貢献。 |
| 十二代 弘入 安政4〜昭和7年 (1857〜1932) |
十一代長男。 明治4年(1872)襲名。 茶道衰退期のため若いときの作品は少なく、晩年になって多数の作品を制作する。 大胆なへら使いに特徴があるとされる。 |
| 十三代 惺入 明治20年〜昭和19年 (1887〜1944) |
十二代長男。 釉薬、技法の研究を歴代中最も熱心に行い、また、樂家家伝の研究を行う。 昭和10年〜昭和17年にそれらの研究結果を『茶道せゝらぎ』という雑誌を刊行し発表。 |
| 十四代 覚入 大正7年〜昭和55年 (1918〜1980) |
十三代長男。 昭和15年、東京美術学校(現・東京芸術大学)彫刻科卒。 彫刻の理論を生かした立体的造形は他代には見られない特徴とされる。 昭和53年、樂家歴代史料を基に「樂美術館」開設。 同年文化庁より無形文化財指定。 |
| 十五代 楽吉左衛門 昭和24年〜 (1949〜) |
京都府立朱雀高等学校、東京芸術大学彫刻科卒。 イタリアローマ・アカデミア留学。 昭和56年(1981)11月襲名。 日本国内外で数々の賞を受賞し、「陶芸作家」としての評価も高い。 1997年、織部賞を受賞。 |
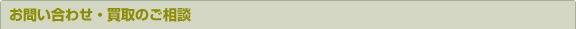
-
美術品買取に関するお問い合わせや美術品買取のご相談は、メール・お電話などでお気軽にどうぞ! 美術品買取のご相談は定休日も含めて毎日AM9:00〜PM9:00まで受付けております。
メールにて画像を添付してお問い合わせいただく場合は、 yakata-@mb.infoweb.ne.jp
までお願いいたします。(メールソフトが起動します)