美術品買取|古美術やかた【京都・東京】
美術品取り扱い一覧
日本美術 金工細工と彫刻
日本の文化には、古来より仏像や刀装具があり、 和式独自の侘び寂び文化が根付いております。
時代が江戸から明治に変わり、世界博覧会に出品された作品は、 その素晴らしさを全世界より賞賛され、その中でも根付や彫刻、金工細工、また七宝焼等 世界に誇れる品物が多くあります。
金工細工
金属工芸は、金属を材料に細工をほどこす工芸のいち分野です。 特に日本では、昔より刀装具類のように独自に栄えた文化があります。
彫金
彫金とは、たがね(鏨)を用いて金属を彫ることです。 プラチナ、金、銀、銅、真鍮、鉄、アルミ、錫などの金属を主材料にして作ります。
彫金の技法は、
地金を図案に沿って糸鋸や鏨で切り取ったり、彫り抜く「透かし」
鏨を用いて地金を彫り模様や図案・文字を入れる「彫り」
地金の裏から大きく打ち出した後、表から細部を押さえていく「打ち出し」
本体の地金に意図する図案の溝を彫り、別の地金を嵌め込む「象眼」などがあります。
七宝焼
七宝焼は、金、銀、銅などの金属製の下地の上に釉薬を乗せたものを、 高温(800度前後)で焼成することによって融けた釉薬によるガラス様あるいはエナメル様の美しい彩色を施しているものです。
中近東で技法が生まれ、シルクロードを通って、中国に伝わり、さらに日本にも伝わりました。
彫刻
彫刻とは、美術的な鑑賞を目的として、様々な素材を用いて制作された立体作品を意味します。 一般的に鑑賞を目的として制作されたものであり、生活用具に用いられる工芸品や陶芸品など、 実用性あるものは除かれることが多いようです。
彫刻に使われる素材は、石、木、土(粘土、テラコッタ)、繊維、紙、氷といった自然のものから、 石膏、金属(鉄、銅など)、樹脂(合成樹脂)、ガラス、蝋などの人工物も含まれ、複数の素材を組み合わせる作品も多々あります。
彫刻の中でも、ブロンズ彫刻と呼ばれるものは、彫刻家の製作は石膏でできた「石膏原型」までで、 それ以降のブロンズ化は「鋳造師」と呼ばれる職人の仕事となります。
そのため石膏原型があれば複製が可能であるため、彫刻家が存命のうちにその承認の下に鋳造された作品を「生前鋳造」、 没後(死後)に鋳造された作品を「没後(死後)鋳造」として厳密に区別されます。
「生前鋳造」こそが本物であり、例えばロダン作の「考える人」は、現在数多くの美術館で見ることができますが、 ロダン美術館によって真正品と認定されているのは世界に21体しかありません。
またオブジェ とは、主に美術用語として用いられ、自然物、工業製品、廃品、日用品など、またはそれを使用して作られた作品を意味します。
現在では、彫刻と呼ぶべき作品があまりに多様化しているため、「彫刻」という用語にそぐわないケースも多く、 単に「立体」「立体アート」と呼ぶこともあるほか、設置空間全体へ拡散し「空間表現」「インスタレーション」と化したものもあり、表現手段も多様化しています。
根付
日本独自の根付細工は、江戸時代に煙草入れ、矢立て、印籠、小型の革製袋などを紐で帯から吊るし、 持ち歩くときに用いた留め具のことです。
材質は堅い木(黄楊、一位、黒檀等)や象牙などがあり、 江戸時代から近代にかけての古根付と、昭和、平成の現代根付に大別されます。
江戸初期のものは簡素なものが多いですが、江戸時代中期に入って、実用性と共に装飾性も重視されるようになり、爆発的に流行しました。
この頃から細かい彫刻が施されるようになり、根付自体が美術品として収集の対象となりました。
明治時代に入ると海外から高い評価を得ており、「根付」の持つ高い芸術性は、現在でも世界中の多くの人々から日本独特の精緻的文化として認められています。
取り扱い作家一覧
当店の今までお取引のあった近代の金工細工・彫刻作家の一部をご紹介いたします。
彫刻
金工
その他
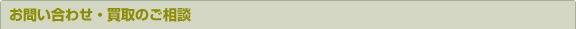
-
美術品買取に関するお問い合わせや美術品買取のご相談は、メール・お電話などでお気軽にどうぞ! 美術品買取のご相談は定休日も含めて毎日AM9:00~PM9:00まで受付けております。
メールにて画像を添付してお問い合わせいただく場合は、 yakata-@mb.infoweb.ne.jp
までお願いいたします。(メールソフトが起動します)